�C�ۗ\��m�����̌X���Ƒ�
���Z�����̃X�X��
�悤������������Ⴂ�܂����I
������ł́A���ۂ̎��Z�����̌`���ł܂Ƃ߂܂����B
�C�ۗ\��m�����̕��ɂ��𗧂ĉ������B
 �����Ƃ��
�����Ƃ�� 
���̃y�[�W�́A2013�N7��2���ȍ~�A�L�����e�̍X�V������Ă���܂���B
���݂̏��Ƃ͈قȂ镔�������݂���\��������܂��̂ŁA��ϐ\���������܂��A���̎|�������̏�ł���������K���ł��B
 �����Ƃ��
�����Ƃ�� 
���̃y�[�W�ł́A�{���ȊO�̂����Ȃ�ړI�̎g�p���֎~�Ƃ����Ē����܂��B
���A���̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă������A�Y�t�}�\�́A���ۂɋC�ۗ\��m�����ŏo�肳�ꂽ���̂��Q�l�ɂ��č쐬���Ă���܂��B
�����̐S�� �i�c�莞�ԁF--���j
���Z�����́A���͂�}�\�ʼn����L�q���ł��B
��������1���i13:10�`14:25�j����2���i14:45�`16:00�j�ɕ�����Ă��āA���ꂼ��75�����ƂȂ��Ă��܂��B
�ƌ����Ă��A2�̑�ނɂ��Ă̖�肪�o�肳��邾���ŁA���ɉ������ς���ł͂���܂���B
�w�Ȃ���15�������ł����A����ł����Ԃ�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������ł��B
���Ȃ��Փx�͍����ƌ����Ă����ł��傤�B
���āA�w�Ȏ������I���ƁA�҂ɂ�65���̃C���^�[�o�����^�����܂��B
���Ȃ��͂��̎��Ԃ��ǂ̂悤�Ɏg���܂����H
���Z�����̒��O�`�F�b�N��������A���H��H�ׂ���A������ƈꕞ������A���������U����A �ܘ_���Ȃ��̎��R�ł����A���͒��H��H�ׂ邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�ߌォ��̎��Z�����́A3���Ԃɂ킽�钷����ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ă͐�͂ł��ʁA�ƌ�����ł��B
�A���A���܂�H�߂���Ǝ������ɖ����Ȃ��Ă��܂��̂ŁA��7���ڈʂɂ��Ă����܂��傤�B
���H��H�ׂ���́A������������Ȃ�A���O�`�F�b�N��������Ȃ肷��Ƃ����ł��傤�B
�Ƃɂ����A���Z�����Ɍ����āA���S�̑Ԑ��ŗՂ݂܂��傤�B
�n�߂�O�� �i�c�莞�ԁF--���j
�����̑O�ɁA�܂��K�v�ȕ������̏�ɑ����܂��傤�B
�w�Ȏ����́A�[�A�M�L�p��A���v�����ł悩�����̂ł����A���Z�����͈Ⴂ�܂��B
�����v���ɏ����Ă��鎝�����݉\�ȓ�������Ă݂�ƁA
�[�AHB�̉��M�i���̓V���[�v�y���V���j�A�v���X�`�b�N�������S���A�F���M�A�}�[�J�[�y���A��K�A
�f�o�C�_�[�i���x��A���̓R���p�X�j�A���[�y�A�y�[�p�[�N���b�v�A���v�i�v�Z�@�@�\�̕t���Ă��Ȃ����́j�Ƃ���܂��B
���̓��A�F���M�A�}�[�J�[�y���A��K�A�f�o�C�_�[�́A���Z�����Ŏg���\��������܂��B
�F���M�A�}�[�J�[�y���́A�}�\�̏����Ɏg���܂��B
��K�A�f�o�C�_�[�́A�}�\�̉�͂Ɏg���܂��B
�K�v�ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����A���Ȃ����g�����ǂ����͕ʂƂ��āA��������ł����đ��͂Ȃ��ł��傤�B
���āA���p�����z��ꂽ��A�܂����ӎ����ɖڂ�ʂ��܂��傤�B
�����肫�������e�ł����A�����J�n�܂ŃC���^�[�o��������̂ŁA�C���𗎂���������̂Ɏg���܂��傤�B
�ܘ_�A�p���Ɏԍ��Ǝ����������̂�Y�ꂸ�ɁB
�ԈႦ��Ɩ����ɂȂ����Ⴄ�̂ŁA���x���m���߂܂��傤�B
�S�ď����������A��͎����J�n�̍��}��҂݂̂ł��B
�}�\�̏��� �i�c�莞�ԁF75���j
�����A�������̍��}�Ŏ��Z�������n�܂�܂����B
���Z�����ł́A�����̎����i�}�\�j���z�z����܂��B
�ƌ����Ă��A�����}�\�́A���p���ɕt���Ă���̂ŁA�܂������藣���܂��傤�B
�~�V���ڂ��t���Ă���̂ŁA�܂�ڂ�t���Ă���A�����܂Ƃ߂Đ藣���Ă����܂��傤�B
�����J�n�Ɠ����ɁA�F��Ăɐ藣���n�߂�̂ŁA�����ɂ��̉��������n�舳���ł��B
���߂Ă̕��́A������Ƃт����肷�邩������܂��A�C�ɂ��Ȃ��悤�ɁB
�����y�[�p�[�N���b�v�������Ă�����A�܂Ƃ߂�̂Ɏg���Ă������ł��傤�B
���āA�S�Ă̐}�\��藣������A�}�\�̏������n�߂܂��傤�B
�����Ŕz����V�C�}�̓��m�N���Ȃ̂ŁA���̂܂܂��Ɣ��ɕ�����ɂ����ł��B
�����ŁA�O���Ő��������F���M�A�}�[�J�[�y�����g���āA�V�C�}�ɐF�h������܂��B
�ǂ���ł������̂ł����A�ł���ΔZ�W�̂������F���M�̕��������ł��傤�B
�܂��A���A���A�i���j�̐F���M��p�ӂ��܂��B
�F�h�������ɂ������āA�Ԃ͒�C�����̈�A���g�O�����A�͍��C�����̈�A����O�����A
��0���A�W�F�b�g���A���������A�Ƃ����l�Ƀ��[�������߂Ă����܂��B
�����ŁA�e�V�C�}���āA�F�h��̃|�C���g�������܂��B
�n��V�C�}
�C���z�u�̊T�v�̔c���ɗp���܂��B
�܂��A���{�t�߂ɉe������������C������ŁA���C������Ń`�F�b�N���܂��B
�X�ɁA�C��Z���x�� FOG [W]���ߌ��i�g���j����Ŕ����h��܂��B
���̐}�Ɋւ��ẮA����ȂɐF�h�肷��K�v���͂Ȃ��ł��傤�B
�n��C���E�~���ʁE���\�z�}
���E��C���̐����A�ړ��A�~���ʁA���̊m�F�ɗp���܂��B
�܂��A���{�t�߂ɉe������������C������ŁA���C������Ń`�F�b�N���܂��B
�X�ɁA�~���\�z�̈�i�_�����j����Ŕ����h��܂��B
�����āA���̖�H����A���̗�������ŕ`�܂��傤�B
���A���̐}�ɂ͑O�����`����Ă��܂���̂ŁA���̐}�𗘗p���đO���̈ʒu����͂��A
���g�O����Ԑ��A����O������ŋL�����܂��傤�B
�ڂ����O���̉�͖@���������B
850hPa ���E�������ʗ\�z�}
����O���̉���ɗp���܂��B
�O���̉�͂ɂ́A�������̐}���K�v�ł����A�܂����̐}�ł��̖ڈ���t���܂��B
���������ʐ�������ł��鏊���炻�̓�[�t�߂��O���ɂ�����܂��B
������A�����悻�̑O���̈ʒu����͂��A���g�O����Ԑ��A����O������ŋL�����܂��傤�B
�ڂ����O���̉�͖@���������B
�X�ɁA�ċG340K�ȏ�̍��������ʈ����Ŕ����h��܂��B
850hPa �C���E��, 700hPa �㏸����͐}
�����㏸���ɒ��ڂ��܂��傤�B
�܂��A�����㏸�������ŁA
�������~�������Ŕ����h��܂��B�i���l���������͖̂����j
������A�㏸����ƒg�C�ڗ���Ɛ��Q�x��A���~����Ɗ��C�ڗ���ƕ��Q�x�悪�ǂ��Ή����Ă��邩���m�F���܂��B
�X�ɁA��̋��ꂪ����-6���ȉ��̒n�����Ŕ����h��܂��B
�����āA�����Ԃ��n���C������ŁA�n�㍂�C������Ń`�F�b�N���܂��B
���A�O���̉�͂ɂ��g���܂��B
������������ł��鏊�╗���������Ă��鏊�����āA
���g�O����Ԑ��A����O������ŋL�����܂��傤�B
�ڂ����O���̉�͖@���������B
500hPa �C��, 700hPa �����\�z�}
�Η������w�̑�C�̋C���Ǝ����ɒ��ڂ��܂��傤�B
�܂��A���̋��ꂪ����-36���ȉ��̒n�����Ŕ����h��܂��B
���A�g�C��iW�j����ŁA���C��iC�j����Ń`�F�b�N���Ă������ł��傤�B
�X�ɁA�����i�C���|�I�_���x�j��3���̐�����łȂ���܂��B
�����āA�����Ԃ��n���C������ŁA�n�㍂�C������Ń`�F�b�N���܂��B
500hPa ���x�E�Q�x��͐}
500hPa�̃g���t�A���b�W�ƉQ�x�ɒ��ڂ��܂��傤�B
�܂��A�����x������ɐ��ꉺ�����Ă��镔���i�g���t�j�ɐ��ő����������A
�k�ɐ���オ���Ă��镔���i���b�W�j�ɐ��ő��W�O�U�O���������܂��B
�ڂ����g���t�E���b�W�̉�͖@���������B
�X�ɁA���Q�x�̈����ŁA���Q�x�̈����Ŕ����h��܂��B�i���l���������͖̂����j
�����āA�����Ԃ��n���C������ŁA�n�㍂�C������Ń`�F�b�N���܂��B
��������ɁA�n��̍��E��C���̏�Ԃ��m�F�ł��܂��B
�Ⴆ�A�n���C���ɑΉ�����g���t��傫�Ȑ��Q�x������A ���ꂪ���㑤�i�����j�ɌX���Ă���ꍇ�́A���̒�C���͊����ňȌ�X�ɔ��B����ƕ�����܂��B
�c����i���Q�x�̈�j���͂ފO�g���Q�x0���ŁA���������W�F�b�g�C�����O���̉�͂��ł��܂��B �����Q�x0������łȂ���܂��傤�B
�ehPa ���w�V�C�}
���x�A���x�A�����i850hPa, 700hPa�̂݁j�A�����E������������Ă��܂��B
850hPa �ł͑O���̉�́A700hPa �ł͎���̔c���A500hPa �ł͑Η������w�ɂ������C�̓����̔c���A
300hPa �ł͑Η�����w�ɂ������C�̗���̔c���ɗp���܂��B
������������ł��鏊�╗���������Ă��鏊�����āA ���g�O����Ԑ��A����O������ŋL�����܂��傤�B �ڂ����O���̉�͖@���������B
850hPa, 700hPa�ł́A�����i�C���|�I�_���x�j��3���̐�����łȂ���܂��B
���A500hPa, 700hPa �ł́A�����x������ɐ��ꉺ�����Ă��镔���i�g���t�j�ɐ��ő����������A
�k�ɐ���オ���Ă��镔���i���b�W�j�ɐ��ő��W�O�U�O���������܂��B
�ڂ����g���t�E���b�W�̉�͖@���������B
�~�G�̏ꍇ�́A���C�̋����⋭�����ɒ��ڂ��܂��傤�B
300hPa �ł́A�W�F�b�g�C���̎�����Ő��������A
�~�G�ɂ����錗�E�ʂ��w�����C������Ń`�F�b�N���܂��B
�ȏ�ŐF�h��͏I���ł��B
���炸����ƐF�h��̃|�C���g����ׂ܂������A������S���`�F�b�N����K�v�͂���܂���B
�n�b�L�������āA�S���F�h�肵�Ă�����A�����������Ԃ������Ȃ��Ă��܂��܂��B
���A�e��薈�Ɏg�p����}�\���w�肵�Ă���܂��̂ŁA
�K�v�Ȏ��ɁA�K�v�ȕ���������F�h�肷��悤�ɂ��܂��傤�B
�������A�}�\��ǂނ̂ɑS���x�Ⴊ�Ȃ��̂Ȃ�A�F�h�肷��K�v�͂Ȃ���ŁA
���Ȃ��ɂƂ��āA��Ԏ��Ԃ��|����Ȃ��Ă������@��I��ʼn������B
�����}�\����ɁA�C�ی��ۂ̎��ԕω��A�ʒu�ω���c�����܂��B
�C�ی��ۂ�3�����̍\���������Ă���̂ŁA�����e�w�̓V�C�}�𗧑̓I�ɗ������邱�Ƃ��K�v�ł��B
�\���𗧑̓I�ɗ�������ɂ́A�V�C�}���d�ˍ��킹�Ă݂����Ƃ���ł��B
���̍�Ƃׁ̈A���Z�����ł��g���[�V���O�y�[�p�[�i�������̎��B����ɏ������ނƉ��̎��Əd�˂Č��邱�Ƃ��ł���j���z�z����܂��B
����́A�C�ی��ۂ̎��ԕω��A�ʒu�ω����݂�̂ɕ֗��Ȃ̂ŁA�L���ɗ��p���܂��傤�B
�����ߖ�� �i�c�莞�ԁF65���j
���Ƃ��ẮA���ꂼ���15�`20��i�z�_�F15�`20�_�j�Ƃ������Ƃ���ł��B
�����������A�V�C�̊T���������̌����ߖ��ŁA��1���Ƒ�2�����ɕK���o�肳��܂��B
�n��V�C�}�������āA��C���̈ʒu��A����n�_�̓V�C����ǂݎ�����A�Ƃ����������ł��B
�ȉ��ɗ��������܂��B
�y��� 1�z�i����14�N�x��2����1�� ��1 �ގ����j�@��Փx�F����������
19��9���i00UTC�j�̒n��V�C�}�ŁA
���C�����ɂ���䕗�̎����ƍ���̗\�z���q�ׂ����̕��͂̋�(1)�`(10)�ɓ��Ă͂܂���܂��͐��l���A�p���ɋL������B
�Ȃ��A1NM�i�C���j��1.85km�A1KT�i�m�b�g�j=1�C��/���ł���B
�� �����͈ŕ����ɂ��Ă���܂��B����ꍇ�́A�J�[�\���ł��̕������h���b�O���ĉ������B
|
�@�����䕗��13���́A19��9���ɂ͔��䓇�̓쐼��120km�̖k��(1)32.3�x�A
���o(2)138.9�x�ɂ����āA(3)���k���ɖ���(4)20(22)km�̑��x�Ői��ł���B
���S�̋C����(5)960hPa�A���S�t�߂̍ő啗����(6)35m/s�ŁA
���S���甼�a(7)110km�ȓ��ł͕���25m/s�ȏ�̖\���ƂȂ��Ă���B �@�䕗�͈��������������͂�ۂ��Ȃ���i�ތ����݂ŁA19�����O�ɂ͈ɓ������암�i�O��`���䓇�`�����j�̂قڑS�悪(8)�\�����ɓ���A 19�����߂�����[���ɂ͑䕗�̒��S�͈ɓ������암�ɂ��Ȃ�ڋ߂��錩���݂ł���B �@���ׁ̈A�ɓ������암�ł́A�\���A(9)��J�A(10)���g�A�����Ɍ��d�Ȍx�����K�v�ł���B |
�y����z
�n��V�C�}���瓾��ꂽ�f�[�^���쐬���ꂽ�A���C�����̑䕗�Ɋւ���C�ۊT���ł��B
�����ł́A�䕗�̏��Ƃ��ꂩ��\�z����錻�ۂ�������Ă���܂��B
(1)�`(7)�@�n��V�C�}�ɋL����Ă���䕗�̋߂��ɁA���̑䕗�̏�p��ŏ�����Ă��܂��B
���̑䕗�̏���ƈȉ��̗l�ɂȂ�܂��B
�䕗��13���i20XX�N�j�A�ď́F�t�@���t�H���i���I�X��F�����j�A960hPa
�k��32.3�x�A���o138.9�x�APSN�ǍD
���k����12�m�b�g�i=��6m/s=��22km/h�j
���S�t�߂̍ő啗��70�m�b�g�i=������35m/s�j
���a60�C���i��110km�j�ȓ��ŁA����50�m�b�g�i=������25m/s�j�ȏ�
������̔��a170�C���i��315km�j�ȓ��A
���̑��̕����̔��a160�C���i��300km�j�ȓ��ŁA����30�m�b�g�i=������15m/s�j�ȏ�
(8)�@����15m/s�ȏ�̗̈��������A����25m/s�ȏ�̗̈��\����ƌ����܂��B
(9),(10)�@�䕗�̐ڋ߂ŗ\�z�����A���ӁA�x���̕K�v�ȋC�ی��ۂł��B
���͋L�q������L�[���[�h�ŗp�����邱�Ƃ������̂Ŋo���Ă����܂��傤�B
�y�z�_�z
�e��1�_�A�v10�_���_�B
�V�C�}����ǂݎ��͂Ɗw�Ȏ����̒m���i�p��j���K�v�Ȗ��ƌ�����ł��傤�B
�z�_��1��i1�̌��j�ɂ�1�_�ŁA���Z�����̒��ł���Փx�͈�ԒႭ�A�������Ԃ�������Ȃ��̂ŁA
�����Ď�肱�ڂ����Ƃ̖����l�A�葁���m���ɐ������Ă����K�v������܂��B
�V�C�L���̌���
���{�ɂ����ēV�C�L���́A���{���ƍ��ێ����g���Ă��܂��B
���{���V�C�L��
�V���Ȃǂł悭����V�C�}�ɂ́A���̓��{���V�C�L�����g���Ă��܂��B
�����ȕ\�L�@�����}�Ɏ����܂��B
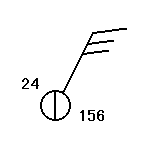 |
���{���V�C�\�L�̗� �V�C�F �� �����F �k�k�� �����F 3�i3.4�`5.5m/s�j�i7�`11kt�j �C���F 24�� �C���F 1015.6 hPa |
�V�C�L���͈ȉ��̒ʂ�ł��B
| �� | ���� | �S�_��0�`1 |  | �� | �S�_��2�`8 |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | �S�_��9�`10 | �� | �J | �ʏ�̍~�J |
| ���L | ���J | ����̉J | ���j | ��J | �ꎞ�I�ȍ~�J |
 | �� | �Z���������� |  | �� | ���a1cm�����̐�̉� |
 | � | ���a1cm�ȏ�̕X�̉� | ���c | �J���� | ���x�̍~�J |
 | �� | �ʏ�̍~�� |  �j �j | ��� | �ꎞ�I�ȍ~�� |
 | ���J | �������~�J |  | �� | ���ɂ�鎋��1km���� |
 | ���� | ���ɂ�鎋��1km���� |  | �o���� | �o�ɂ�鎋��1km���� |
 | ���o�� | �����ɂ��o�̐����グ�Ŏ���1km���� |  | �n���� | �����ɂ���̐����グ�Ŏ���1km���� |
���ێ��V�C�L��
�S���E���ʂ̓V�C�L���ł��B
�����ȕ\�L�@�����}�Ɏ����܂��B
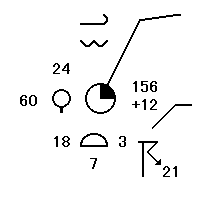 |
���ێ��V�C�\�L�̗� ���݂̓V�C�F ���i�_���U�j�A�ߋ��̓V�C�F ���J�A�~���ʁF 21mm �S�_�ʁF 2�`3�A���E���w�_�ʁF 3�i2�`3�j ��w�_�F ���_�A���w�_�F ���ω_�A���w�_�F �ω_ �Œ�_���F 7�i1,500�`2,000m�����j �����F 10km�i�����L�Q�Ɓj �����F �k�k���A�����F 10KT�i5.0m/s�j �C���F 24���A�I�_���x�F 18�� �C���F 1015.6hPa �ߋ�3���Ԃ̋C���ω��ʁF +1.2hPa �ߋ�3���Ԃ̋C���ω��X���F �㏸��A���i�܂��͊ɂ₩�ɏ㏸�j |
�� �����i����j�F 0��0.1�q�����A0�`50�́i���l��10�j�q�A56�`80�́i���l�]50�j�q�ɂē��o�B�i51�`55�͎g�p���Ȃ��j
�� �����i�C��j�F 90��0.05km�����A91��0.05km�A92��0.2km�A93��0.5km�A94��1km�A95��2km�A96��4km�A97��10km�A98��20km�A99��50km�ȉ��B
�V�C�L���͈ȉ��̒ʂ�ł��B
| �S�_�� | �_�` | ||
|---|---|---|---|
| �� | 0 |  | ���_ |
 | 1�ȉ� |  | ���w�_ |
 | 2�`3 |  | ���ω_ |
 | 4 | �� | ���w�_ |
 | 5 |  | ���ω_ |
 | 6 |  | �w�ω_ |
 | 7�`8 |  | ���w�_ |
 | 9�`10���� |  | �ω_ |
| �� | 10 |  | �Y��ω_ |
 | �s�� |  | �ϗ��_ |
 | �ϑ��@��Ȃ� |  | �w�E�ω_�f�� |
| �\ | �w�_ | ||
| ���݁E�ߋ��V�C | ���� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | �� |  | �_���U |  | 酉J�i��j |  | ���キ |
| �� | ���� |  | ��͗l�s�� |  | 酉J�i���j |  | 5KT |
| s | �o���� |  | �_���B |  | �� |  | 10KT |
 | ���o�� |  | ���� |  | 50KT | ||
| �� | ���� |  | ���J | �Œ�_�̒�̒n�ʂ���̍��� | |||
| �� | �� |  | �X�R�[�� | /: �s���A0: 50m�����A1: 50�`100m���� | |||
 | ���J | �E] | �J������ | 2: 100�`200m�����A3: 200�`300m���� | |||
| �E | �J�i��j | �d | ��J�i�A���j | 4: 300�`600m�����A5: 600�`1000m���� | |||
 | ��i��j | �� | �J�i���j | 6: 1000�`1500m���� | |||
 | � |  | �J�i���j | 7: 1500�`2000m���� | |||
 | ���d |  | ���J�i�A���j | 8: 2000�`2500m���� | |||
 | �n���� |  | �� | 9: 2500m�ȏ�A���͉_���Ȃ� | |||
�� ��Ɋւ���L���́A�J�̋L���Ɛ�̋L����u�������邾���ׁ̈A�ȗ����Ă��܂��B
�������ݖ�� �i�c�莞�ԁF55���j
�K��1��͏o�肳��܂��B�i�z�_�F5�`20�_�j
��C���̓��i�ߒ���O���̉�̖͂�肪�����o�肳��Ă���悤�ł��B
�ȉ��ɗ��������܂��B
�y��� 2�z�i����15�N�x��1����1�� ��1 �ގ����j�@��Փx�F����������
500hPa ���w�V�C�}�ɂ�����g���t�̈ʒu�������ŁA���b�W�̈ʒu��g���i�W�O�U�O���j�ŋL������B
�y����z
�g���t�ƃ��b�W�́A������C���̒J�ƋC���̔����̂��Ƃł��B
�g���t�͋C�����J��ɒႭ�Ȃ��Ă��镔���ŁA���b�W�͋C����������ɍ����Ȃ��Ă��镔���ł��B
�����n��V�C�}�Ō���Ɠ��������A500hPa, 700hPa���̍��w�V�C�}�Ō���Ɠ����x�����A
��ɐ��ꉺ�����Ă��镔�����g���t�ŁA �k�ɐ���オ���Ă��镔�������b�W�ƂȂ�܂��B
�o�������Ƃ��ẮA500hPa�ʂ̏�w�g���t�E���b�W�̉�͂��l�����܂��B
��͕��@�́A�ȒP�ɁA�g���t�̏ꍇ�͊e�������̓�[�A���b�W�̏ꍇ�͊e�������̖k�[����Ō��Ԃ����ł��B
��́A�������������ł��邱�Ƃ�A�g���t�̏ꍇ�͌�ʂɊ��C�ڗ��A
���b�W�̏ꍇ�͌�ʂɒg�C�ڗ������邱�Ƃ���A���������s���܂��B
�܂��A��͂����g���t����ɁA�n��̒�C���̏�Ԃ����邱�Ƃ��ł��܂��B
���̃g���t���n���C����萼�ɂ���A�����x���������x�����ׂ��œ�ɐ��ꉺ�����Ă���i���C�ڗ�������j�ƁA
���̒�C���͔��B����ƌ����܂��B
����A�g���t���n���C���Ɠ��ʒu�A���͓��ɂ���A�����x���������x�����ׂ��œ�ɐ��ꉺ�����Ă��Ȃ��ƁA
���̒�C���͐��n�A���͐��シ��ƌ����܂��B
���i�O���̉�͖@�̍��j�Ƀg���t�E���b�W��͐}�i��C���̔��B�Ə�w�p�^�[���j�������܂��B
�y�z�_�z
�g���t�i�����j�A���b�W�i�g���j�Ƃ���3�_�A�v6�_���_�B
�}�\�ɏ������ގ��ɁA���s���낵�ĉ����Ǝ��Ԃ�������܂����A����ȕK�v�͂���܂���B
�̓_�Ɋւ����� 6.�ɂ�����悤�ɁA
�ǂݎ��덷�����l�����āA�����ɂ͓K�ȕ��̋��e�͈͂�݂��Ă����ׁA
���Ȃ����ǂݎ�����ʂ�ɁA���������߂����̂ł��B
����Ȃɓ�Փx�͍����Ȃ��̂ŁA�ł��邾���葁���m���ɐ������Ă����܂��傤�B
�O���̉�͖@
��ʓI�ɁA�g�C�Ɗ��C���Ԃ���ʂ�O���ʂƂ����A���ꂪ�n�\�Ɛڂ������O���ƌ����܂��B
�O���ʂ�O���͂�����x�̌��݂╝������܂����A�O���i�ʁj�͉��x�X�x���s�A���Œg�C�ɐڂ��鏊�̓���Ƃ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�O���ʂ���ɂ́A��C���x����������̂ł����A����͒��ڑ���ł��Ȃ��̂ŁA
�C���A�I�_���x�A���ʁA�������ʓ��ő�p���܂��B
�O�������݂���ꏊ��������|�C���g�Ƃ��Ď��̂��Ƃ��������܂��B
- �C���̒J�̒��ɑ��݂���B �� ��C���̎��ӂ�T���܂��傤�B
- ���������}�ς���B�i��C����]�A�����j �� �O���ƕ������͂قڒ������Ă��܂��B
- �C�����A�I�_��������B �� ���̊ԂɑO�������݂��܂��B
- �����ɍ�������B �� ���̊ԂɑO�������݂��܂��B
- �C���ω��X���ƕω��ʂ��قȂ�B �� �O�����ړ����Ă���ꍇ�A�O�ʂʼn��~�A��ʂŏ㏸���܂��B
- �~���̏�_�̕��z���قȂ�B �� �ω����鏊�ɑO�������݂��܂��B
- �������A�����ʐ��A���������ʐ������݂����Ă���B �� ���̓�[�t�߂��O���ɂ�����܂��B
����܂��āA�V�C�}���g���ĉ�͂����Ă݂܂��傤�B
�܂��A850hPa ���E�������ʗ\�z�}���g���āA��L 2. �� 7. ����A�����悻�̑O���̈ʒu����͂��܂��B
���ꂩ��A850hPa �C���E��, 700hPa �㏸���\�z�}���g���āA��L 2. �� 3. �� 7. ��я�̏㏸������A
500hPa ���x�E�Q�x�\�z�}���g���āA�Q�x0���t�߂�����������s���܂��B
�Ō�ɁA�n��C���E�~���ʁE���\�z�}���Q�l�ɂ��A�ŏI�I�Ɍ��肵���O���̈ʒu���������݂܂��B
�������̓V�C�}���d�ˍ��킹�Ă݂�̂ŁA�g���[�V���O�y�[�p�[���g���ƕ֗��ł��B
�������A���̎�������ł��O����͂��ł��܂��̂ŁA�������Q�l�ɂ��܂��傤�B
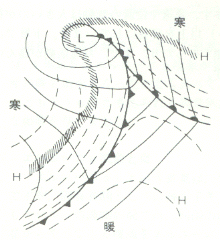 |
�O����͐} �_���F850hPa�̓������A�����F�n��̓������A �A�e�F��w�i500�܂���300hPa�j�̑O�� |
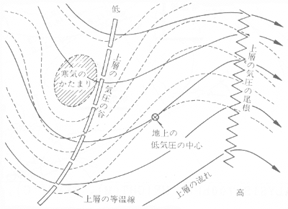 |
�g���t�E���b�W��͐} |
��C���̓��i�ߒ�
�O���̑O����͂ƃZ�b�g�ŏo�肳��邱�Ƃ�����܂��B
�n���C�������݂���ꏊ��������|�C���g�Ƃ��Ď��̂��Ƃ��������܂��B
- �C���̒J�̒��ŁA�C������ԒႭ�Ȃ��Ă��鏊�B
- ���������ŁA����������C����]�ŁA�������Ă���B
- ���������ŁA�����㏸�C��������B
- ����̒��ŁA�~���ʂ������B
- �������A�����ʐ��A���������ʐ����k�ɐ���オ���Ă��鏊�̐�[�B
����܂��āA�V�C�}���g���ĉ�͂����Ă݂܂��傤�B
�܂��A�n��C���E�~���ʁE���\�z�}����A���������̒�C���̈ʒu���m�F���܂��B�i�k��t�߁j
�����A����͐��x�̒Ⴂ���̂Ȃ̂ŁA���̐}���g���Ĕ�����������K�v������܂��B
500hPa ���x�E�Q�x��͐}�ł͐��Q�x�̍ő�l�A
500hPa �C��, 700hPa �����\�z�}�ł͏�L 4. �� 5. ����A
850hPa �C���E��, 700hPa �㏸����͐}�ł͏�L 2. �� 3. �� 5. ����A
850hPa ���E�������ʗ\�z�}�ł͏�L 2. �� 5. ����A�ŏI�I�ɒn���C���̈ʒu�����肵�܂��B
�A���A���֍s���قǒʏ�Q�ǂ�㏸���͐��ɌX���Ă���ׁA���ӂ��K�v�ł��B
����獂�w�V�C�}�́A�����܂Ŕ������ŗ��p���܂��傤�B
�������̓V�C�}���d�ˍ��킹�Ă݂�̂ŁA�g���[�V���O�y�[�p�[���g���ƕ֗��ł��B
�W�F�b�g�C���̉�͖@
�W�F�b�g�C����200�`300hPa�ʕt�߂Ɏ�������A
��ʓI�ɓ��{�t�߂ł́A���уW�F�b�g�ƈ��M�уW�F�b�g��2�������܂��B
�����W�F�b�g����̕����������邱�Ƃ�����A��͂����W�F�b�g�C����2�Ƃ͌���܂���B
���200�A250�A300hPa���w�V�C�}��A�_��͏��}�A�_�摜�����͂��܂��B
200�A250�A300hPa���w�V�C�}�ł́A�����������`����Ă��܂��B
���̓�����������A�������̈ʒu���m�F�ł��܂��B
�X�ɁA���������Ɠ������̍���ł���ꏊ����A�W�F�b�g�̈ʒu�f���邱�Ƃ��ł��܂��B
�܂��A�_��͏��}��_�摜����A�V�[���X�X�g���[�N���g�����X�o�[�X���C���A �È�i��w�̊�����j�̑��݂��`�F�b�N���܂��B
���̑��ɂ��A500hPa�̉Q�x0����A�����C�摜�̈È�i�k���j�Ɩ���i�쑤�j�̋��ړ��������͂��邱�Ƃ��ł��܂��B
���͋L�q��� �i�c�莞�ԁF35���j
���Z�����̔����ȏオ���̖��ł��B�i�z�_�F60�`80�_�j
���Z�����̒��ł���Փx�͍����A�d�v�Ȗ��Ǝv���܂��B
�ȉ��ɂ������̗��������܂��B
�Ȃ��A��Ɋ܂܂���L�[���[�h�������ŋL���Ă��܂��B
�y��� 3�z�i����15�N�x��1����2�� ��3 �ގ����j�@��Փx�F����������
500hPa �C��, 700hPa ����24����, 36���ԗ\�z�}��
850hPa �C���E��, 700hPa �㏸��24����, 36���ԗ\�z�}�ɂ��A
5���̓����A�{�錧���s�ŐႪ�~��\���͏������ƍl������B
���̗l�ɔ��f����鍪����70�����x�ŏq�ׂ�B
�Ȃ��A�K�v�ɉ������n��̋C���Ǝ��x�ɂ��J�ᔻ�ʐ}�y���G�}�O�����𗘗p����B
�܂��A���w�͖O�a���Ă��āA�C�������͎����f�M�����Ɠ����ł���Ƃ���B
�� �����͈ŕ����ɂ��Ă���܂��B����ꍇ�́A�J�[�\���ł��̕������h���b�O���ĉ������B
|
850hPa�\�z�}�ł͐��s�̋C������0���ȏ��ł���A
�����艺�������f�M�����ŋC�����㏸����ƒn��ł���8���ȏ��ŁA�Ⴊ�~��C���ł͂Ȃ��B�i70���j |
�y����z
��ʓI�ɁA���{���̉_�̒��͕X�_���ŁA�X���i��̗��j��蹂���̏�Ԃł��B
�������A����炪�������āA�C����0�x���Ă���ƁA�Z���ĉJ�ɂȂ�܂��B�i�₽���J�j
���̖��̏ꍇ�A850hPa �C���E��, 700hPa �㏸��24���ԗ\�z�}�i5��9���j���A
850hPa�Ő��s�t�߂̋C���͖�0���ł��邱�Ƃ��m�F����܂��B
��36���ԗ\�z�}�i5��21���j�ł́A��3���ȏ�ł��邱�Ƃ��m�F����܂��B
���ł́w�����Ⴊ�~��\���x�ƂȂ��Ă���ׁA��0���ȏ��ł���Ƃ��܂��B
��������X�ɗ�������ꍇ�A���w�͖O�a���Ă���ׁA�C���������f�M�����ŏ㏸���܂��B
�n��̋C����m�邽�߂ɁA�������G�}�O�������g���܂��B
�܂��A�C��850hPa�ƋC��0���̐��̌�_���v���b�g���A�������������f�M���i�j���j�ƕ��s�Ȑ��������܂��B
���̐���1000hPa�i���̐}�\����͒n��̋C����������Ȃ��ׁA�����n��C���Ƃ���j�̌�_�̋C���͖�8���ł��邽�߁A�n��̋C���Ǝ��x�ɂ��J�ᔻ�ʐ}���A
�Ⴊ�~��C���ł͂Ȃ��ƌ����܂��B
�y�z�_�z
850hPa�ʂł̋C���A�����f�M�����ŋC�����㏸�����邱�ƁA�n��̋C���Ƃ���2�_�A�v6�_���_�B
�y��� 4�z�i����15�N�x��2����1�� ��1 �ގ����j�@��Փx�F����������
500hPa�V�C�}�ł́A�T�n�����̓��Ɠ��{�C�����ɒ�C������͂���Ă���B
�������A�n��V�C�}�y��700hPa,850hPa�V�C�}�ł́A
�T�n�����̓��ɂ͒�C������͂���Ă��邪�A���{�C�����ɂ͒�C������͂���Ă��Ȃ��B
�e�����ʂł̋C�����Q�Ƃ��A���{�C�����ʼn��w�ɒ�C���������Ȃ��Ȃ闝�R��90�����x�ŋL�q����B
�� �����͈ŕ����ɂ��Ă���܂��B����ꍇ�́A�J�[�\���ł��̕������h���b�O���ĉ������B
|
500hPa�ł͓��{�C�����ƃT�n�����̓������x�͂قړ��������A
�����艺�w�ł͓��{�C�����̕����C�����Ⴍ��C���x���傫���̂������ʊԂ̑w���͏������A
���w�قǒ�C���������Ȃ��Ȃ�B�i90���j |
�y����z
��w�̊���Q�i�����C���j�Ɋւ�����ł��B
���̒�C���̒��S�t�߂͎��͂�艷�x���Ⴂ�̂ł����A�X�ɋC�����Ⴂ�̂́A�����C���̏���̑Η����E�ʂ�����ŁA
���̏�̉������w���̉��x�����͂�荂������ł��B
���āA���̖��ł̉̃|�C���g�Ƃ��ẮA���w�i500hPa�j�����w�i700hPa,850hPa,�n��j�̈Ⴂ�����A ������A�@���Ȃ闝�R�Œ�C������͂���Ă��Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃɂ���܂��B
�܂������x���Ō���ƁA500hPa�ł͓��{�C�����ƃT�n�����̓��̒�C���̍��x�͂قړ������ł����A
700hPa�`850hPa�`�n��ł̓T�n�����̓��̕������x�i�C���j���Ⴍ�A�����x�i���j�������Ă��܂��B
�܂�A�T�n�����̓��̕��͉��w�`���w�܂ł̔w�̍�����C���ƂȂ��Ă���A���{�C�����̕��́A���w�݂̂̒�C���ł��邱�Ƃ�������܂��B
���ɁA�e�����ʂł̋C��������ƁA���w�`���w�܂ň�т��ē��{�C�����̕����C�����Ⴍ�Ȃ��Ă��܂����A
���w�ɍs���قNjC���̍����傫���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B
�V�C�}���番���邱�Ƃ͂��ꂾ���Ȃ̂ŁA���ɒ�C������͂���Ă��Ȃ����R���l�@���܂��B
���R�Ƃ��čl������|�C���g�Ƃ��ẮA���{�C�����̕������w�ɍs���قNjC�������Ⴍ�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B
�C�����Ⴂ�ƁA��C�̖��x�͑傫���Ȃ�A�̐ς��������Ȃ�܂��B
�܂�A���w�قǓ��{�C�����̕�����C���x���傫���A�����ʊԂ̑w�����������Ȃ��Ă���ƌ����܂��B
����͍��C���̐����ł���A����ĉ��w�قǒ�C���͌����Ȃ��Ȃ�܂��B
�y�z�_�z
500hPa�ʂł̍��x���A500hPa�ȉ��̉��w�ł̋C�����Ƃ���2�_�A
�C�����Ⴂ�Ƒ�C���x���傫�������ʊԂ̑w�������������Ƃ�4�_�A�v8�_���_�B
�y��� 5�z�i����14�N�x��2����1�� ��4 �ގ����j�@��Փx�F����������
�E���Ɏ����}A�Ɛ}B�̖�H�Ɣ��������̌����ɒ��ڂ��A���ꂼ��̗̈�ɂ�����g�Q�̂����A
��z����g�Q�����ƌĂԂ��i�g�Q�̎�ށj���A���̐��������ꂼ��20�����x�ŋL�q����B
�Ȃ��A���ꂼ��̗̈�̋ߊC�ɂ͑䕗���߂Â��Ă�����̂Ƃ���B
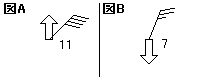
�� �����͈ŕ����ɂ��Ă���܂��B����ꍇ�́A�J�[�\���ł��̕������h���b�O���ĉ������B
|
�}A�F ���˂� �����F �䕗���ӂŔ��������g�Q���`�d�����B�i17���j |
|
�}B�F ���Q �����F ���̗̈�Ő������ɂ�萶�����B�i15���j |
�y����z
�g�Q�}�Ɋւ�����ł��B
��H�͕��́E�����A���������͑�z�g���A�����͑�z�����i�b�j��\���܂��B
�ő��ɏo�肳��Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�p���}�̓ǂݎ��������`�F�b�N���Ă����܂��傤�B
�o��p�x���Ⴂ���Ƃ�����A��Փx�͒Ⴂ�ƌ��Ă����ł��傤�B
�܂��p��������āA���̈Ӗ���₤�`���̖��ł��B
���̗p��𗝉����Ă���A����������Ƃ��ł��܂��B
�}A�͕����Ɣg�����t�̌����Ȃ̂ŁA���̏�̕��Ƃ͕ʂ̗͂ɂ��g�������Ă���ƍl�����܂��B
���̔g�Q���䕗�ɋN��������̂ł���A���̖��̏ꍇ�A�����Ƃ���̂ŁA�䕗�Ɨ��܂������K�v�ƂȂ�̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�}B�͕����Ɣg�������������Ȃ̂ŁA���̏�����ɂ���Ĕg�������Ă���ƍl�����܂��B
�y�z�_�z
�g�Q�̎�ނ͊e2�_�A�����͊e3�_�A�v10�_���_�B
�̓_�Ɋւ����� 4.�� 5.�ɂ�����悤�ɁA
���̖��ł́A�L�[���[�h�̗L�����d�v�ł��B
����āA�܂����L�[���[�h�������܂��傤�B
���͋L�q���ɂ͎�������������܂����A��������20�������L�[���[�h��1���ƍl���ĉ������B
���͂����ɂ������āA�L�[���[�h�𗅗������ł͂������_���ŁA
�L�[���[�h�𗝘_�I�ɐ������g���K�v������܂��B
���������Ɋւ��ẮA�����ʂ��x�X�g�ł����A��������8�`12���܂łȂ炢���ł��傤�B
���߂����菭�ȉ߂����肷��ƁA�]�v�Ȏ��������Ă�����A
�K�v�Ȏ���������Ă��Ȃ������肵�Ă���\��������̂ŁA���������K�v�ł��B
�v����ɁA�ݖ�ŋ��߂�ꂽ���Ƃ������܂��B
�]�v�Ȏ��������Ă��Ă��̓_�̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂��A���_�I�ɊԈ���Ă���ꍇ�́A���_�̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�܂��A�ݖ�Ŏw�����ꂽ�}�⎑���Ɋ�Â��ē����܂��傤�B
�w������Ă��Ȃ��}��p������A�t�Ɏw�����ꂽ�}��p���Ȃ��́A���_�̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ�����܂��̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�G�}�O�����̉�͖@
�G�}�O�����Ƃ́A����n�_�̏���M�͊w�I�Ɍ�����Ԑ}�̂��Ƃł��B
��ɂ���n�_�̉��������̑�C����x���݂�ׂɗp�����܂��B
�����ɂ͋C�����A�c���ɂ͍��x�̑���ɋC���̎��R�ΐ����Ƃ��Ă���܂��B
�����āA�E������̂قڒ����������������f�M���Q�ŁA
��������X���̑傫����_�����������f�M���Q�ŁA
�X�ɌX���̑傫���_�������O�a��������Q�ł��B
�����f�M���Q�ɂ����ʁi�Ɓj���A�����f�M���Q�ɂ��������ʁi��w�j��10K���ɁA ���O�a��������Q�� g/kg �P�ʂ��������̒l���L����Ă��܂��B�i���}�Q�Ɓj
�}�̉E��̐����`�́A���̃G�}�O������̕��������͂ޖʐς��\���G�l���M�[�iJ/kg�j�̑傫����\���A ���̐����`�̖ʐς�400 J/kg �ɑ������܂��B
����n�_�̂��鍂�x�ŋ�C��̋C���Ɖ��x�����肳�ꂽ��A
���̒l���G�}�O�����Ƀv���b�g���܂��傤�B�i�_ 1 �j
���̋�C���f�M�I�ɏ㏸���������̉��x�ω��́A�_ 1 ��ʂ銣���f�M������ɒH��Ε�����܂��B
�t�ɁA���ɒH���āA1000hPa���ƌ�������_�������i�_ �Ɓj�ł��B
�����䂪�������Ă���ꍇ�́A�����f�M������ɒH���āA���̍�����Ɠ��l�̓��O�a��������ƌ�������_�i�_ 2 �j���A
��C�O�a���������グ�Ì����x�ł��B
���ꂪ�قډ_��̍��x�ɑ������܂��B
������X�ɏ㏸���������̉��x�ω��́A�_ 2 ��ʂ鎼���f�M������ɒH��Ε�����܂��B
�t�ɁA���ɒH���āA1000hPa���ƌ�������_�����������i�_ ��w�j�ł��B
�����f�M������ɒH���āA0�i�[���j�̓��O�a��������Ƃ̌�_�ŁA��C��͊��������邱�ƂɂȂ�܂��B�i�_ 3 �j
��������A�����f�M�������ɒH����1000hPa���ƌ�������_�����������i�_ ��e�j�ł��B
�܂��A�I�_���x���������Ă���ꍇ�́A���̓_��ʂ铙�O�a��������̒l��������ƂȂ�̂ŁA���̒l���g�p���܂��B
�I�_���x�i�_ Td�j���瓙�O�a�����������ɒH���āA
�_ 1 ��ʂ銣���f�M���ƌ�������_���_ 2 �ƂȂ�܂��B�i�E���}�Q�Ɓj
���̗l�ɁA�G�}�O������p���Ă��낢��ȔM�͊w�̗ʂ��v�Z���邱�Ƃ��ł��܂��B
�d�v�Ȏ�����1�Ȃ̂ŁA�����̏o��p�x�͍����Ǝv���܂��B
�G�}�O��������A���̒n�_�̏��̏�Ԃ𗝉��ł���悤�ɂ��Ă����܂��傤�B
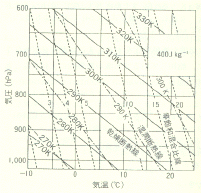 |
�G�}�O�����t�H�[�}�b�g |
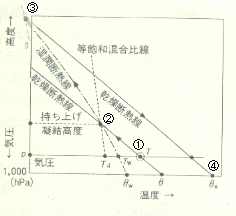 |
�G�}�O������͐} |
��C����w���̌v�Z�@
��C�����������ŗ͊w�I�Ɉ��肩�ǂ����́A�C�ی��ۂ̔����E���B�ɂƂ��ďd�v�ȗv����1�ł��B
��C�̈���x�́A�����A�����A�s�����ƒ�`����܂��B
�����C���������ɉ^�������ہA���̈ʒu�ɖ߂邩�A�ϓ����Ȃ����A
�]�|���N�������ɂȂ�܂ʼn^�����p�����邩�A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B
����́A�^��������C�����x�i���x�j���A���͂̑�C�������x�i���x�j�ɔ�ׂāA �Ⴂ���A�������A�������Ŕ��f���邱�Ƃ��ł��܂��B
���݁A�ȒP�ɉ������萫�����ς���w�W�Ƃ��āA�V�������^�[�̈���w���iSSI�j������܂��B
�V�������^�[�̈���w���iSSI�j�́A850hPa�̋�C���500hPa�ʂɒf�M�I�Ɂi�O���Ƃ̔M�̂���肪�Ȃ���ԂŁj�����グ��Ɖ��肵�A
�����グ��ꂽ��C��̉��x Tc �����͂̑�C�̋C�� Te ���獷�������� �iTe-Tc�j �̒l���A1���P�ʂ̐��l�Ŏ��������̂ł��B
���̒l���}�C�i�X�i���j�ł���ƁA�����グ��ꂽ��C��͕��͂čX�ɏ㏸���邱�Ƃ���A �����Ɂi�×͊w�I�Ɂj�s����ȑ�C�ƌ����܂��B
�����グ�����C��̉��x�����߂�ɂ́A850hPa�̋�C���O�a�̏ꍇ�͊����f�M�I�Ɂi�r���ŖO�a�����ꍇ�́A���̐�͎����f�M�I�Ɂj�A �O�a�̏ꍇ�͎����f�M�I�Ɏ����グ��Ƒz�肵�āA���̉��x�ω������߂܂��B
�V�������^�[�̈���w���iSSI�j���}�C�i�X�i���j�ŁA���J�����ɗv���ӂƂȂ��Ă��܂����A
���l�\��̌��ʂ�p����ꍇ�́A�덷���l�����āASSI < 3�ł��ꉞ���ӂƂ���ƂȂ��Ă��܂��B
�����̏o��p�x�͒Ⴂ�Ǝv���܂����A�O���̃G�}�O�����ƃZ�b�g�ł̏o�肪�l�����܂��B
�����I�� �i�c�莞�ԁF0���j
�����A�c�莞�Ԃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���͑S���������ł��傤���H
�����̐l�́A�ł��邾���������������ޓw�͂����܂��傤�B
�L�[���[�h�̗���ł̓_���Ȃ悤�Ȃ̂ŁA�m���ɐ����ł������Ȗ��Ƀ^�[�Q�b�g���i���āA ����������邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
���ς�ł���l�́A�̓_�Ɋւ����̒��ӎ������v���o���Ȃ���A ������ƑS�̂��������Ă����܂��傤�B
���������c�A�ԍ��Ǝ��������m�ɏ�����Ă��邩���m�F���Ă����ĉ������ˁB
�����āA�������̍��}�Ŏ��Z�������I���܂����B
�F�����l�ł����B
���i�Ɏ��M�̂���l���Ȃ��l���A������Ɩ��������A���āA
��10��������c�@�l �C�ۋƖ��x���Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ō��\�����͔͉ƏƂ炵���킹�ĉ������ˁB
���Ȃ݂ɁA���̃y�[�W�̗��͑S����40�_���_�ł��B
28�_�ȏ�Ȃ獇�i�A�ƌ��������Ƃ���ł����A�����_�����Ȃ�Â��Ǝv���̂�32�_�ȏ��͗~�����Ƃ���ł��B
�s���i���ۂ��l�͎���Ɍ����āA���i���ۂ��l�͏����Ɍ����āA �ǂ��������Ȃ������̂����A������ƌ������A���Ȃ��Ă����܂��傤�B



