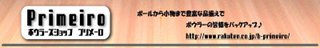みなみの一からボウリングレッスン
4-1 ラインアジャスティング
マイボウラー上級編 【適正アベレージ:181〜190】
このページはマイボウラー上級の方のみ御覧下さい。
レーンに合わせて投げる
ここまで来られた方は、フォームも固まり、安定した投球ができるようになっていると思います。
でも、それだけでは、所詮アベレージは180止まりです。
これより上を目指すには、「レーンに合わせる」レーンアジャスティング技術が必要となってきます。
安定した投球により狙った板目を通るようになったとしても、 所詮人間のすることなので誤差はつきものです。
レーンにオイルが塗られていなかった場合、スパットで板目が1枚ずれただけでも、 60フィート先のピンデッキでボールの当たる位置は、板目4枚分もずれてしまいます。
4枚ずれるとポケットを完全に外してしまう為、高得点を出すのは非常に難しいのが分かります。
でも実際は、例え板目を1枚ミスしても、あまりポケットを外さなくて済むことが多くないでしょうか。
それは、レーンに塗られているオイルの「濃淡」がボールの動きを補正してくれるからです。
|
右の図を見て下さい。 たいていのレーンは、中央部分がオイルが濃く(赤色)、両外側が薄く(黄色)なっています。 青線のラインでポケットインした時、ラインの内(左)側がオイルが濃く、外(右)側が薄い状態であったとします。 もし、内側にミスした場合(緑線)、オイルが濃いので曲がりが抑制されます。 結果、共にミスしていない青線の時と同じポケット付近にヒットしてくれる訳です。 このオイルの「濃淡」を利用してポケットにボールを集めるのが、レーンアジャスティング(レーンに合わせる)ということなのです。 |
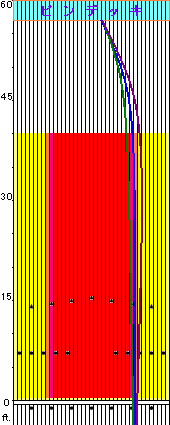 |
ボウリングは、レーンに合わせる競技です。
レーンと喧嘩せず、逆に理解した上で、自分がイメージしたラインの通りに、
ポケットまでボールを運ぶことを考えるようにしましょう。
もし、ボールが想定した動きをしなかった場合は、 「コントロールができていない」、「レーン(オイル)が読めていない」ということになります。
「コントロールできている」というのは、 「フォームが安定しており、ほぼラインに乗せることができる」ということと、 「レーン(オイル)が読めている」という2つの意味があります。
前者と後者の差は、ストライクの数に表れてきます。
前者しかできないボウラーは、スペアボウリングなのでアベレージ180台止まり。
後者もできるボウラーは、ストライクボウリングなのでアベレージ200超えも可能になります。
これからは、如何にストライクの確率を高めるか、ストライクを出し続けるかを考えましょう。
ストライクラインの理想形
ゲームを始めたら、まずしなければならないのは、ストライクラインを探すことです。
すんなり見つかればその日のアベレージは高くなるでしょうし、なかなか見つからなければ低迷してしまいます。
基本的なストライクのとり方は既出なので割愛させて頂いて、 ここでは、よりストライクになるラインの採り方をご紹介します。
みなさん、ハウスボール時代から今まで、ポケットに入っているのにストライクにならなかった、何て経験が何度もあると思います。
逆に、ポケットに入ってないのにストライクになったこともあると思います。
後者はピンアクションによるものですが、これを利用すれば、ちょっとポケットからズレても、ストライクになる確率が高くなります。
ピンアクションは運次第の様に思えますが、意図的にこれを引き起こすことはできます。
ピンにヒットした時点で、ボールが滑っていたり、ただ真っ直ぐ転がるだけになっていなければ、ピンアクションが良くなります。
それを踏まえた上で、私が理想とするストライクラインは図の通りです。
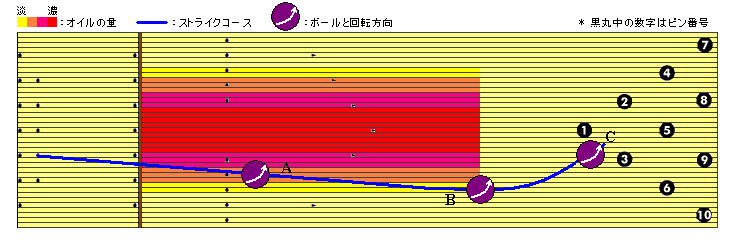
初めはオイルゾーンを通し、ボールを走らせ(スピードを維持させ)ます。(A)
オイルゾーンから出してフックさせます。(B)
回転軸が寝る(完全な縦回転になる)前にポケットへヒット!(C)
フッキングポイントは、入射角5°になるように、且つ、回転軸が寝る前にポケットへヒットするように調整します。
曲がらずに滑ったままだったり、早く曲がってロールアウト(ただ真っ直ぐ転がるだけ)してピンにヒットすると、
ボールの威力が死んでしまい、良いピンアクションが得られません。
威力が落ちてタップになったり、スプリットになったりします。
ボールが曲がり切った直後くらいで、ポケットへヒットさせる感覚でいいと思います。
オイルの分布状況を見極める
初級編でスパット理論を使ってボールを通すラインを決めると言いましたが、
実際のレーンでは、その通りに投げても実際ボールが通るラインにはズレが生じます。
その原因は、レーンに塗られているオイルの分布にあります。
では、どの様にラインを決めればいいのか?
私は、スパット理論は参考程度で、実際のライン調整で使うことはありません。
1度投げたラインにおいて、ボールがどの様な回転・動きをしたかで、
そのライン付近のオイル分布状況を推測し、次の投球ラインを考えます。
初めの内は、見るのが難しいかもしれませんが、慣れればリリース直後から分かるようになりますので、 是非頑張って観察できるようになって下さい。
観察するポイントは、次の4つです。
リリース直後からスパットまでの間
リリースによって生じた回転がほとんど変化していないかどうかを見ます。
ここはオイルゾーンを通るべきなので、ボールの回転が緩いはずです。
回転速度が上がったり、回転方向に変化が見られるようだと、そこはオイルが削れているので、 いわゆる「噛む」状態となり、この先での動きが期待できません。
スパットからレーンの中間付近
回転に若干の変化が徐々に表れてきたどうかを見ます。
ここも基本はオイルゾーンを通るべきなので、回転が緩いままですが、
実際は、徐々に摩擦が掛かり始めるので、回転数が上がり、回転方向に変化が出てきます。
しかしこの段階では、パッと見にはあまり変化しているようには見えません。
もし、見た目で明らかな程に回転が早くなり、軌道も内側に逸れるようであれば、 そこはオイルが削れているので、いわゆる「噛む」状態となり、この先での動きが期待できない上、 早く曲がり過ぎたりして、イメージしたラインから大きく外れてしまう結果となります。
この先のコンディション(オイル分布状況)にもよりますが、 基本的にはここは走らせて、その後、徐々にボールが「起き上がる」(回転が変わる)ようにする方がベターです。
フッキングポイント前後
フッキングにより、ボールの進行方向が変わるポイントを確認します。
オイルゾーンを抜けると強い摩擦が掛かり、ボールの回転方向にボールの進行方向が変わっていきます。
レーンコンディションを見極める上で最も大事なポイントなので、投球毎にこの位置確認をするようにして下さい。 (板目を多く跨ぐラインを採る場合は特に!)
フッキングの仕方により、生きたボールが投げられたかどうかは自分の感覚で分かりますが、 同じ生きたボールでも、キレがあるとその辺りのオイルはほとんどない状態、 キレがなく緩く曲がるようだとキャリーダウンが進行している状態だと分かります。
フッキングポイントからピンにヒットするまでの間
ボールの進行方向が変わってからピンにヒットするまでの回転を見ます。
最後まで滑った状態(横回転が残ったまま)だったり、完全な縦回転(ロールアウト:ただ転がっている状態)だったりすると、
ボールの破壊力は半減するといってもいいでしょう。
ロールアウトになる直前にピンにヒットさせるのがベストです。
ピンアクションや残りピンを見て、ラインアジャストすることもできますが、それはまた後程…。
とりあえずは、だいたいでもいいのでボールの転がり方を最後まで見れるようになって下さい。
▼ 【ボウリング講座】ボールの回転からレーンコンディションを読む - YouTube
幅のあるラインを見つける
前にも言いましたが、人間のすることなのでコントロールミスはつきものです。
でも、それを最小限に抑えることができれば、オイルの濃淡を利用して、
ボールの動きを補正することができます。
最初は、狙いのスパットより「内側外側とも2枚以内」に抑えられるようにしましょう。
それができるようになったら、「内側1枚以内、外側2枚以内」を目指し、
最終的に、「内側外側とも1枚以内」に確実に投げられるようになって下さい。
実際のレーンでは、内側外側1枚以内の誤差なら、 幅のあるストライクラインさえ見つけることができれば、ストライクを連発できるようになります。
問題はそのラインの探し方ですが、 クラウンレーンとブロックレーンの場合は、基本的にはまず「オイルの壁」(オイルが濃いゾーンと薄いゾーンの境目)を探します。
そこより内側のラインでは、オイルが濃い為ボールが滑っていき、 外側のラインでは、オイルが薄い為ボールが噛んでしまいます。
その中間のオイルの壁に通せば、 もし内側にミスった場合、オイルが濃いので曲がりが抑制され、 外側にミスった場合、オイルが薄いので曲がりが大きくなり、 結果、ミスってない時と同じ所にヒットしてくれます。
次に、ヒットポイントがポケットじゃないと意味がないので、 立ち位置やスパットを1枚ずつずらして、ポケットに持っていくラインを探します。
もちろん、この間にオイルの壁から完全に外れてしまっては、これまた意味がありません。
しっかり生きたボールでポケットにヒットするように、ラインを調整します。
フラットレーンの場合は、そのままでは幅が使えません。
なので、暫くは幅はないけど生きたボールでストライクにできるラインを投げ続け、
キャリーダウンしたところで、そのキャリーダウンを「オイルの壁」に使います。
こういう作業を「レーンを作る」と言います。
クラウンレーンやブロックレーンにおいても、キャリーダウンやブレイクダウンを利用し、
幅のあるラインを形成することができます。
ちなみに、内ミス外ミスの補正は、オイルの濃淡だけではありません。
内ミスすれば、親指が抜け損ねているので、フィンガーに掛からず、回転力が落ちてあまり曲がらず、
外ミスすれば、親指がすっぽ抜けているので、フィンガーに掛かりすぎて、回転力が上がって余計に曲がる、
という要因もあります。
▼ 【ボウリング実験】オイルの壁を使ってポケットに集める - YouTube
【練習】様々なラインを投げ分ける
アベレージ190以上の上級者ボウラーになる為に必要な要素は、「ストライクボウリング」「イメージ」「アジャスト」です。
「ストライクボウリング」は、常にストライクを狙うボウリングをすること。
ストライクをより多く、また連取することが、一番スコアが伸ばせる方法なのですから当然です。
「イメージ」は、経験よる鋭い読みでラインをイメージすること。
いくらライン通りに投げられる技術を持っていても、そもそもレーンが読めていなければ、求める結果は得られません。
「アジャスト」は、読み間違えた、またはコンディションの変化によりずれたラインを、素早く的確に微調整すること。
このアジャストができてこそ、目指すストライクボウリングができるようになるのです。
必要なのは、何といっても経験です。
実際に投げた経験を得て、様々なコンディションに対応できる様な「引き出し」を増やしていきましょう。
一番いいのは、コンディションの変化が激しい「競技会(大会)」に出場することですが、 普段の練習においては、ジャストストライクラインだけではなく、以下のような様々なラインを投げてみましょう。
ジャストストライクライン
立ち位置:板目 枚目、スパット:板目 枚目
内絞りライン【オイルゾーンの中を突っ切る】
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
外出しライン【内側のオイルゾーンから外側のドライゾーンへ出す】
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
オイルの壁沿いライン【オイルゾーンとドライゾーンの境目に沿わせる】
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
クロスライン【外側のドライゾーンから内側のオイルゾーンにぶつける】
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
大外ライン【外側のドライゾーンを走らせる】
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
| 立ち位置:板目 枚目 | スパット:板目 枚目 | 結果: |
ラインを色々変えてみて、できればポケットにもって行けるようにして、
その都度、ボールの軌道、ピンアクションをじっくり観察するのです。
こう投げたら、割れやすい、タップになりやすい、この入射角なら少しずれてもストライクになりやすい等、色々見えてくるはずです。
また、ストライクになるラインが複数存在することもわかると思います。
実戦では、一番幅があるラインを採用することもあれば、オイルを温存する為、敢えて外の若干難しいラインを採用する等、状況に応じたラインの選択をすることが可能になります。
練習においては、逆に幅があまりないラインを見つけて、ひたすら投げ込むのもいいでしょう。
より厳しい状況での練習をすることで、より自らの実力が磨かれていくはずです。