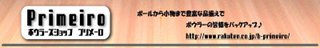みなみの一からボウリングレッスン
4-2 レーンの攻め方を考える
マイボウラー上級編 【適正アベレージ:191〜205】
このページはマイボウラー上級の方のみ御覧下さい。
投球毎にライン取りをする
これまでにも述べてきた様に、レーンコンディションは、生き物の様に刻々と変化していきます。
それなのに、ストライクが続くからといって、同じラインばかり投げていたら、 遅かれ早かれ、そのラインではストライクが獲れなくなってきます。
例え今は良くても、まだゲームが続くのならば、先のことも考えて投げる必要があります。
プロやアマチュア上級者の投球を見ていると、常にポケット薄めのラインを狙っていることがよく見受けられます。
これは、スプリットのリスクを減らす意味もありますが、この先のことも考えて、できるだけ内側のオイルを使わないようにもしているのです。
内側のオイルは壁になるので、これを残しておくと、後半のゲームでもラインの幅を使えて有利になります。
逆に、前半からジャストポケットを狙ったり、内壁を頼った投球をしていると、後半は内壁が削られてしまい、難しい投球を迫られることになります。
キャリーダウンやブレイクダウンを予測し、的確に先手を打てるようになれれば、 ゲームを有利に進め、おのずと勝負にも勝てるようになってくるでしょう。
とは言え、先手を打つのは、もちろんリスクを伴います。
初めの内は失敗続き、ということもあるでしょう。
それでも自分の感性を信じて、ラインを動かしていってください。
経験を積めば積むほど、失敗は少なくなり、投球毎に的確なライン取りができるようになってくるはずです。
初期状態の攻め方
「初期状態」は、メンテナンス直後である為、
ヘッド(手前)はオイルがしっかりあって、バックエンド(奥)はしっかりクリーニングが効いています。
つまり、「手前はボールがよく走り、オイルが切れるとボールが急に曲がり出す」という訳です。
まず、ボールはアーク状に曲がる(レスポンスタイムが長い、ゆったり曲がる)タイプがいいでしょう。
走って切れるボールだと、切れすぎてロールアウトしてしまいがちになります。
ラインの採り方ですが、前項でも述べた通り、内側のオイルをあまり使いたくないので、外目のラインを使います。
あと、ストレートライン(板目に沿って投げるライン)ではなく、ややオイルが濃いゾーンから少し薄いゾーンへ出してあげた方がいいでしょう。
できればあまり板目は跨がずに、せいぜい2〜3枚くらいに抑えるのがベターです。
板目を使い過ぎると、内側に大量にあるオイルを奥へ運ぶことになるので、後々の投球が難しくなってきます。
初期状態は、ボールが暴れやすい(コントロールが乱れやすい)ので、あまり打ちやすい状態とは言えません。
キャリーダウンしてレーンが落ち着くまでは、我慢の投球を心掛けて下さい。
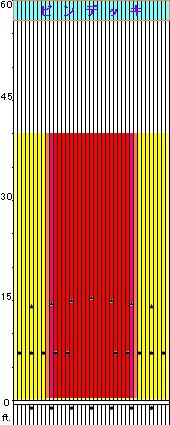 |
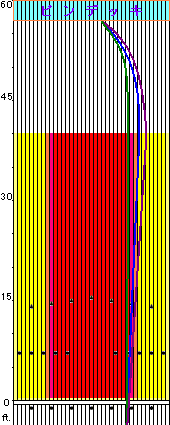 |
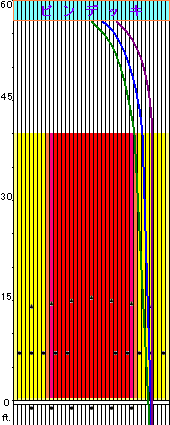 |
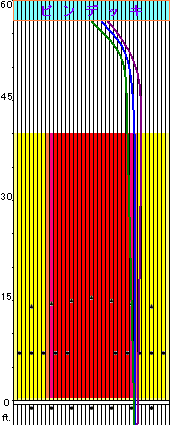 |
| メンテナンスしてから誰も投げていない初期状態。バックエンドがクリーンで、オイルの境目がはっきりしている。 | ストレートかやや外出しラインにすると、ストライクの幅を広げることができる。 あまり板目を跨がない方が良い。 | 外のオイルも感じやすいので、生きたボールが投げられないと、クロスラインを採ってしまい、幅が出せない。 | 曲がり(或いはキレ)が良いボールを使うと、ボール(の動き)が暴れてしまい、 扱いが難しくなる上、幅も出しにくくなる。 |
キャリーダウンの攻め方
「キャリーダウン」は、手前にあるオイルが、投球とともに奥へと引き伸ばされて行く現象のことです。
車が水溜りを通過した直後に、タイヤの濡れた跡が付くのと同じ原理です。
但し、キャリーダウンの跡は消えることがありませんので、 それを計算に入れた上で、ライン取りをしていく必要があります。
初期状態でポケットインしていたラインでも、キャリーダウンしてくると、
バックエンドがオイリーになって、曲がりが徐々に弱くなってきます。
このままではストライクが取れないので、ラインを変えなければいけません。
キャリーダウンを感じたら、基本的には、立ち位置とスパットともに右へ2枚平行移動します。
そこはオイルが薄めのラインですが、移動すると左側にキャリーダウンゾーンを持ってくることができ、 これが内壁の役目を果たしてくれるので、幅を使った投球が継続できる訳です。
これで、ポケットにもって行けても、ボールがロールアウトしてしまう場合は、 立ち位置だけを1枚左へずらす等して、手前の内側のオイルを使ってボールを走らせるといいでしょう。
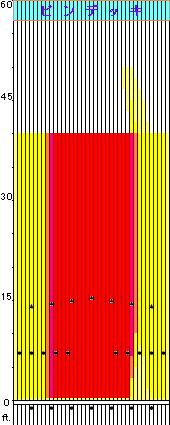 |
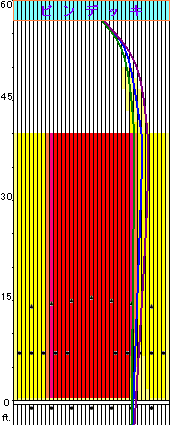 |
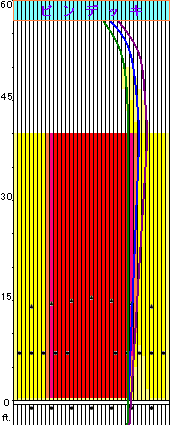 |
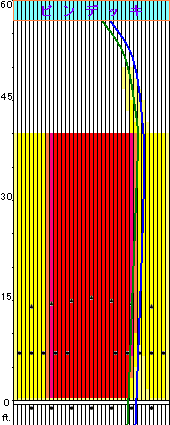 |
| 同じラインを投げ続けることで、手前のオイルが奥に運ばれて行き、バックエンドでのボールの動きが弱くなる。 | キャリーダウンが進む内は、立ち位置・スパットともに右へ2枚ずつ平行移動していくと、継続して幅を使える。 | キャリーダウンが判らないと、曲がらないのは自分のせいだと思い込み、力んで自分の投球を崩してしまう。 | 走りやすいボールでポケットに届かないなら、それより少しオイルに強いボールにしてみるのも一手。 |
ブレイクダウンの攻め方
「ブレイクダウン」は、キャリーダウンが進むと伴に、手前のオイルが削り取られて少なくなっていく現象のことです。
ブレイクダウンしてくると、手前からボールが動き始め(回転が変わり始め)、 想定ラインより中に逸れたり、早くロールアウトしてしまうことで、奥での曲がりが出なかったり、ボールのパワーを損なう結果となります。
このままではストライクが取れないばかりか、スプリット多発の危険性もあるので、早急にラインを変える必要があります。
ブレイクダウンを感じたら、基本的には、立ち位置だけを左へ2枚移動します。
そこはまだ手前のオイルが残っているラインなので、バックエンドまでパワーを維持したままボールを走らせることができます。
また、移動すると右側にブレイクダウンゾーンを持ってくることができ、
これが外ミスを補正してくれる為、幅を使った投球が継続できる訳です。
これで、ボールが走り過ぎてしまう場合は、 スパットだけを1枚程右へずらす等、外へ出すラインの角度を大きくして対応して下さい。
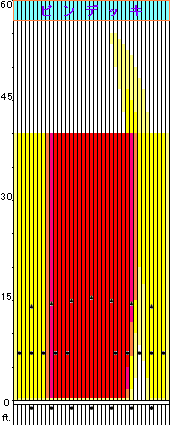 |
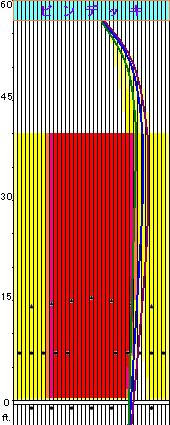 |
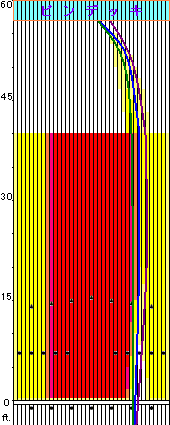 |
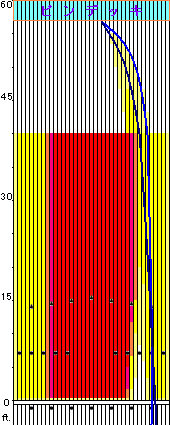 |
| 更に投げ続けると、手前のオイルが擦り減り、薄くなっていく。手前からボールが動き出してしまい、奥でへたれてしまう。 | 外への移動ができなくなったら、立ち位置だけを左へ2枚ずつ移動していくと、継続して幅を使える。 | 手前の枯れたゾーンを通すと、ポケットを突いても、ボールの威力が落ちてしまうので、タップしやすくなる。 | かなり走るボールで、大外あるいはクロスラインを採るのも有効。長期戦で内のオイルを温存したい場合は、こちらがオススメ。 |
ドライ状態の攻め方
「ドライ状態」は、ブレイクダウンが更に進んで、オイルゾーンの奥の方までオイルが削り取られてしまった状態のことです。
こうなってくると、オイルの削れたゾーンやそれより外のラインは、もう使うことができません。
基本的には、立ち位置は2枚ずつ、スパットは1枚ずつ左へ移動していきます。
攻め方はブレイクダウンのときと同じですが、徐々に内壁が削れていくので、
それに伴い、ラインも内側から大きく外側へ出すようにせざるを得なくなります。
ポケットにはもって行けても、角度が出せなくなる上、幅も狭くなってくるので、非常に難しくなります。
かなり走る(ドライレーン用)ボールに持ち替えるのも一つの方法です。
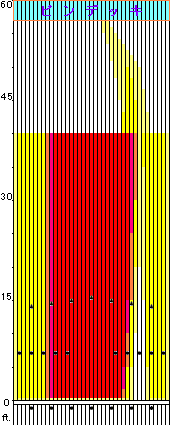 |
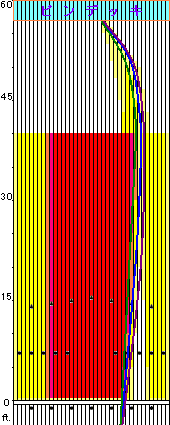 |
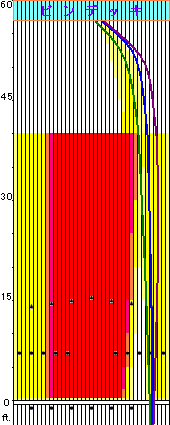 |
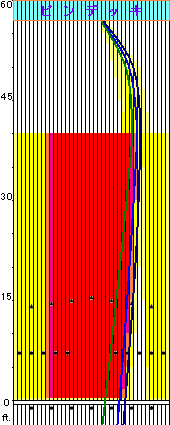 |
| かなりゲームが進むと、手前のオイルがどんどん削られていく。ドライゾーンを避けたライン取りが必要となる。 | ラインを少しずつ左へずらしていき、内側のオイルを削っていく。奥の内壁は、できるだけ温存できるようにする。 | 大外、クロスラインがまだ使えるならいいが、内ミスした時にドライゾーンに掛かると、ミスが増長されてしまうかも。 | 板目を大きく跨がなければならず、ポケット入射角度もつけ辛くなり、ゲーム進行とともにどんどん難しくなっていく。 |
各オイルパターンの攻め方
センターによっても、また時と場合によっても、オイルパターンは違います。
通常の営業レーンなら、これまでご紹介してきた「ブロック型」と下図の左から2つ目の「クラウン型」の 中間的なパターンになっていることが多いです。
この様なレーンは、公平性がある上、スコアが出やすい特徴があります。
人(又はボール)によっては、「ハイスコアレーン」(通称:ハイスコレーン)に感じるでしょう。
他のオイルパターンやオイルゾーンの奥行きの長さによっても、 レーンの攻め方が変わってくるので、以下の4つの例について考えてみたいと思います。
フラットレーン
下図の左端のオイルパターンです。
そう感じることはあっても、実際にフラットでオイルがひかれていることは、ほとんどないと思います。
なので、「フラット」を謳っている競技会などがあれば、出場すると貴重な経験ができることでしょう。
攻め方ですが、オイルの濃淡がないので、最初はストレートライン(ファールラインと垂直)か、やや外出しライン、
または大外ラインを使ってポケットにもって行くしかないと思います。
内壁がないので、内ミスは絶対厳禁です。
外ミスの方が、まだボールが返って来て助かる可能性があります。
オイルが伸びてキャリーダウンしてきたら、その部分を内壁に利用しましょう。
その後は、ブレイクダウンと共に、立ち位置を内側へ移動していきます。
いずれにしても、幅がほとんどないので非常に難しいです。
如何に、スプリットを出さずに、スペアを拾っていけるかが鍵となります。
アベ200以上のボウラーでも、170〜180打てれば上々ではないでしょうか。
クラウンレーン
下図の左から2番目のオイルパターンです。
実際は、図の様に極端なことはなく、前述の様な「ブロック型」との中間的なパターンであると理解して下さい。
攻め方は、ボールの種類や回転にもよりますが、 基本的には、立ち位置よりスパットを数枚外へ出したラインを採るといいでしょう。
キャリーダウン、ブレイクダウンの対応は、ブロック型と同じ(前述の通り)でいいと思います。
このパターンは、オイルの濃淡もありますし、非常に幅が出やすくなっている為、
そのラインさえ見つければ、ミスが補正されてストライクを連発させることができます。
パーフェクトも夢じゃない、これが「ハイスコレーン」たる所以です。
ロングレーン
オイルゾーンの奥行きの長さが長い(42〜45フィート)のをロングレーンといいます。
オイルゾーンの奥行きが長いということは、その分走る距離が長く、曲がる余裕が少ない、ということが言えます。
よって、オイルに強くて、切れのいい(鋭角に曲がる)ボールが適しています。
一番難しいのは、キャリーダウンの時です。
ただでさえオイリーなのが、更に助長される為、「ボールが曲がらない」滑ったままピンまで行くので「パワーがない」ということになります。
そんな場合は、大外のラインを採ると、ボールがドライゾーンを通る長さが長くなるので、
ボールが曲がる余裕ができます。(ただし、ロールアウトに注意が必要です。)
また、内壁が相当分厚ければ、クロスラインを採ることも選択肢の一つとなるでしょう。
いずれにせよ、しっかりと「生きたボール」が投げられることが必要となります。
ショートレーン
オイルゾーンの奥行きの長さが短い(35〜38フィート)のをショートレーンといいます。
オイルゾーンの奥行きが短いということは、その分走る距離が短く、曲がり過ぎてロールアウトしてしまう危険性がある、ということが言えます。
よって、走ってゆったり曲がるボールが適しています。
一番難しいのは、初期状態とドライ状態の時です。
できるだけオイルゾーンを走らせるラインを採って下さい。
自然と内から外に出すラインになると思います。
よって、ストレートやクロスラインは、絶対厳禁です。
内ミスしたときに、内に入りすぎてスプリットになる危険性が高いからです。
ただし、長丁場の場合は、最初からオイルを使い過ぎることは避けたいところです。
なので、できるだけ走る(オイルを感じやすい)ボールで投げる必要があります。
ちなみに、ゲーム単価を安くする代わりに、
オイル量を節約して「ショート」などにしているセンターもあるようですが、
こういうセンターには、慣れ過ぎない様にしましょう。
慣れると、スピードがあっても曲がるので、回転力が身に付いてきません。
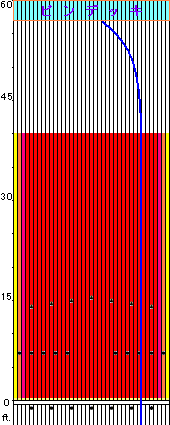 |
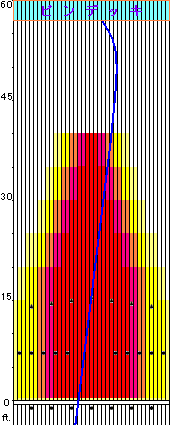 |
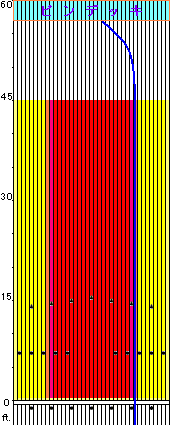 |
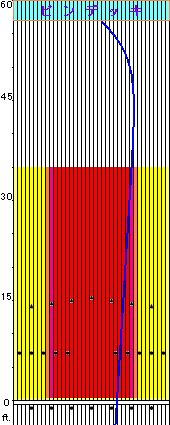 |
| 【フラットレーン】 左右の端から端まで一様にオイルが塗布されたレーン。オイルの濃淡でミスが補正されないため、非常に難しい。特に初期状態が最難関。 |
【クラウンレーン】 内側はオイルが多く、外や奥に行くにつれオイルの量が減っていくレーン。どんなタイプのボウラーにとっても、公平で理想的なレーン。 |
【ロングレーン】 ブロックレーンのロングレングスコンディション。オイルに強い、切れのいい(鋭角に曲がる)ボールが適している。キャリーダウン時が最難関。 |
【ショートレーン】 ブロックレーンのショートレングスコンディション。走ってゆったり曲がるボールが適している。初期状態が最難関だが、ドライ状態でも難しい。 |
【練習】レーンの変化に付いていく
特に、練習メニューはありません。
ただ、大人数(アメリカン4〜5人打ち)で投げるゲームを数多くこなして下さい。
普段の練習ででも構いませんが、競技会に出場するのがベストです。
一緒に投げる人数が増えるほど、自分自身が体感するレーンの変化が早くなります。
そりゃそうですよね。
自分が投げる間に3〜4人が投げるわけですから。
ヘタをすれば1〜2フレームの内にレーンが変化することもあります。
最終的には、これ位の変化スピードに付いて行ければいいですが、
最初の内は、アメリカン3人打ちくらいがちょうどいいかもしれません。
レーンの読みやその変化は、経験でしか得ることはできません。
予備知識は勿論必要ですが、それを実践して体感しないとモノにできないので、
例え成績は悪くとも、続けていけば必ず身に付いてくるでしょう。